| 昔は身体の中にどういう臓器がってどういった働きをし、それが病気にどのように病気に関係があるのか、といった病理や生理の理解は浅く、病人に対する診断方法や選薬方法は、経験や第六感をフルに使って治療していました。 例えば、頭が痛い・節々が痛いなどの症状群。腹痛がある下痢をするといった症状群。さらに、のどが渇く小便が近いなど、病人の訴える自覚的な症状群と、診断する側の他覚的な状態を基に考え、一定の条件を満たせば《A処方》違う条件であれば《B処方》というよに「必要かつ充分なる条件」から症状を求め、選薬していました。古くから使われていたこの診断・選薬方法を【古法】といいます。 あらゆる症状を求めて、条件に準じた薬を服用すれば、病気の原因を治療できる全く理想的な流儀なのです。 |
| 【古法】には問題点がありました。症状群を選び出し条件に合った処方をするにはかなりの経験を要し困難を極めました。時によっては不必要な症状までも診断・選薬基準に入れてしまう可能性が高く、間違いを生じることが多かったのです。【古法】の流儀は満たされる条件を選び出すのが難しく、扱うものは毎回不便さを感じながら治療をしていました。効かない処方はいたしかたないで済んでいた時代はよかったのですが、医学の進歩に伴って【古法】は見直すことを迫られるようになってきました。 簡単に効率よく、正確な診断を求められ、納得できる治療のためには、人の身体にはどのような臓器があり、どのような関係で動いているかを知る必要がありました。そこで人や動物の身体を解剖し、身体の中には五つの臓器、すなわち肝臓・心臓・脾臓・肺・腎臓があり、五つの腑(ふ)すなわち胆のう・小腸・胃・大腸・膀胱があることを見出しました。しかし現在のように、いろいろな検査をする機械や器具はありませんので、詳しい関係性は調べられません。そこで考え出されたのが、「人間は自然の一部」という考えの下、季節や方角、感情や色などが病気に密接な関係があるという経験から、太古から培われてきた【陰陽五行】の考えを身体の臓器に当てはめ、病気の診断・選薬をするようになりました。これが現在の東洋医学の基礎になった【後世法】です。 |
| 万物の自然現象には神秘的な力が働き、その力は決まった循環の下に巡っています。人間のからだも同じ神秘的な力によって互いに助け合ったり、余分な力を抑制しあい調和を保っています。 そういった考えを下に、人間と自然は同じ力によって存在しているのではないだろうか、と結論に達しました。 始めに、自然界を五つの要素「木」「火」「土」「金」「水」に分け、それぞれの関係をまとめました |
|||||||||||||||||||||
|
| 人間は自然の一部であり、自然界の五つの要素を人の臓器に当てはめたのが【後世法】です。 地球上では五つの要素が助け合っていたり、邪魔し合っていることを見出しました。五臓五腑を並べてゆくと肝臓・心臓・脾臓・肺・腎臓を五臓の【陽】とし、胆嚢・小腸・胃・大腸・膀胱を五腑の【陰】にして互いの関係を関連付けて考えるようになったのです。「自然界の五つの要素」と同様に相生・相剋し合い、病気の原因や選薬を正確に判断できるようになりました。 |
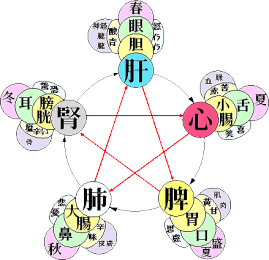 |
このように、【自然界の五つの要素】と同様に配置しました。 実線の矢印が相生関係(助け合う関係)で、点線の矢印が相剋関係(邪魔し合う関係)です。自然界の要素と人間のからだには密接な間関係があり、臓器同士は皆つながっており、一つの臓器の機能が落ちれば全体のバランスにも影響を及ぼします。西洋医学のように細分化された医学ではなく、東洋医学はこの関係を大切に漢方を処方します。 したがって自然な形での体質改善はもちろんのこと、未病、慢性病の治癒にも力を発揮できるのです。 |
 ページの先頭へ戻る |
|
|
| |トップ|店舗紹介|商品案内|東洋医学の変遷|からだのお話|ちゃのま|リンク|特定商取引 |
| Copyright 2006(C) すみれ薬局. All Right Reserved. |